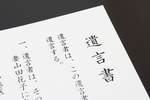市川市、船橋市で相続・遺言・終活なら市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターへお任せ下さい。
市川市内、船橋市内、初回相談料無料・出張費無料・訪問無料相談実施中です!
市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
『終活』に関する34の質問・相談事例
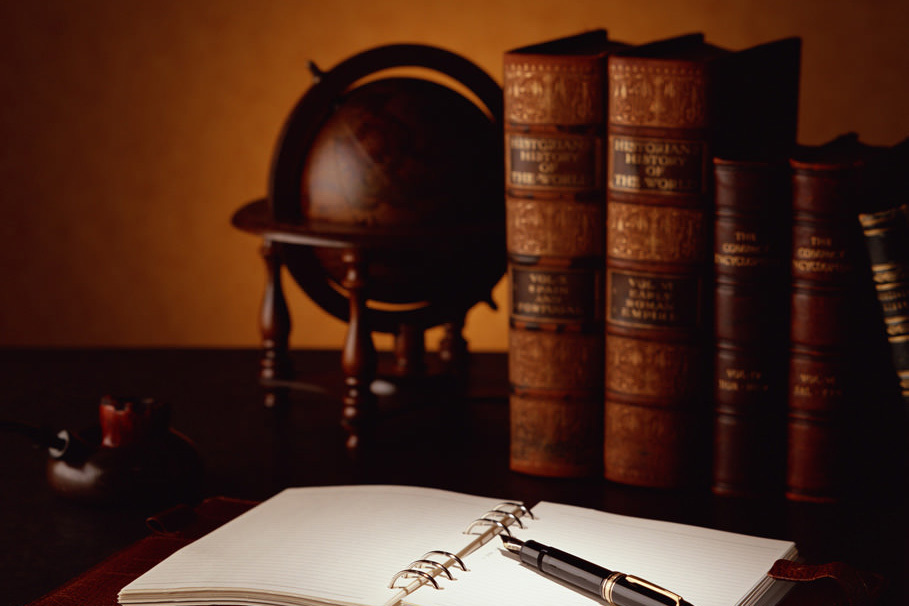
こちらでは、私ども『市川・船橋 相続・遺言相談センター』に寄せられた『終活』に関するお客様の質問・相談事例をご紹介いたします。
『終活』に関する34の質問・相談事例
Q.『終活』とはどういうことをするのですか?
A.『終活』とは法律で定められた定義はありません。当相談センターでは、『老後の生活への備え(生前の備え)、死後の家族への備え(死後への備え)』と考えております。
Q.『終活』にはどのようなものがありますか?
A.大きく分けると、(1)「生前の備え」と(2)「死後への備え」に分かれます。
(1)「生前の備え」として
①体が不自由になったときへの備え
②認知症になったときへの備え
③延命措置・尊厳死への備え
(2)「死後への備え」として
④遺産相続への備え
⑤葬儀納骨などの(遺産以外の)事務手続きへの備え
があります。
Q.「体が不自由になったときへの備え」としてどのようなものがありますか?
A.「体が不自由になったときへの備え」として、『財産管理等委任契約』があります。具体的には、銀行の預金の払い出し手続きや振り込み手続き、病院・福祉施設への支払い手続きなどお金の支払いや管理などについてご自身で家の外に出て行うことが困難になり、誰か代わりに手続きを行ってもらう必要が生じた時への備えです。ここでは、単なるスーパーでの買い物を代わりに行うことは想定しておらず、手続きに本人確認が必要になるような場合を想定しています。昔は、「○○さんの代わりにお金を下ろしに来たのですが」といった場合でも顔見知りであればお金を下ろせたりしたこともあったのですが、現在は、家族さえ代わりに手続きをするには、委任状を要求されたり、本人が来店しないと手続きができなかったりします。このような不都合を避ける方法があります。手続きを委任する『財産管理等委任契約書』を『公正証書』で作成しておけば、役所や金融機関の窓口での手続きがスムーズにできます。当相談センターでは、公正証書にするための『財産管理等委任契約書』の文案をお客様1人1人のご希望を伺って個別に作成しております。
Q.「認知症になったときへの備え」としてどのようなものがありますか?
A.「認知症になったときへの備え」として、『任意後見契約』があります。具体的には、自分が認知症になってしまった場合の財産管理を行う人(後見人といいます)と内容を自分で予め決めておくことができます。この任意後見契約をしておかないで、認知症になってしまった場合には、その時点で「判断能力がない」ことになるので契約を結ぶことはできません。そこで、家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所に成年後見人を選んでもらう必要があります。ここで家庭裁判所が後見人を選ぶ場合は、認知症になってしまった方の財産などを考慮して選ぶので、今まで娘さんに世話になっていたとしても、家族以外の第三者を選任することも多いです。いざという時になってからでは遅いので、今現在、判断能力がしっかりしているうちに誰に頼むか決めておくことをお勧めします。この『任意後見契約』も『公正証書』で作成しますので、認知症になってしまった後でも、金融機関などでの手続きをスムーズにすすめることができます。
Q.「延命措置・尊厳死への備え」としてどのようなものがありますか?
A.「延命措置・尊厳死への備え」として、『尊厳死宣言公正証書』があります。脳の機能は停止しているにもかかわらず、さまざまな延命治療で人工的に生かされることを拒む旨を、担当の医師や家族に口頭ではなしをしていたとしても書面が残されていなければ延命措置を受けざるを得ないのが現実です。そこで、無用な延命措置をやめてほしいという希望があるのであれば、その意思を客観的に表明できる『尊厳死宣言』を『公正証書』で作成しておくことをお勧めします。
Q.「遺産相続への備え」としてどのようなものがありますか?
A.「遺産相続への備え」としては、皆様ご存じの『遺言書』があります。こちらも『公正証書』で作成することをお勧めします。いざ相続手続きをする段階になったとき、公正証書で作成していた場合は、数通の書類を取得すれば良いのに対し、自筆証書遺言の場合は、出生から死亡までの除籍・原戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書など多くの書類が必要になり、かつ家庭裁判所における遺言書の検認手続きも必要になります。手続きの簡便さが全く違います。残された家族のことを思うからこそ、『遺言書』は『公正証書』で作成しておくことをお勧めします。
Q.「葬儀・納骨などの事務手続きへの備え」としてどのようなものがありますか?
A.「葬儀・納骨などの事務手続きへの備え」として、『死後事務委任契約』があります。こちらは、遺言書ではできない事項について、死後に本人の生前の希望をかなえるための契約になります。具体的には、葬儀・納骨・医療費の清算・福祉施設の清算・賃貸住宅の解約・電気・ガス・水道の解約・名義変更・家財道具の処分などです。これらは、身寄りがない人や親族と疎遠になっている人にとって、他人の手を煩わしてしまうことはもちろん、身近に家族がいる人であっても、相続人にどのような方法が望ましいか意見が対立することも多く、以降の家族関係の紛争のきっかけになることが非常に多いので、生前にしっかり定めておくことが紛争防止に極めて役に立ちます。
Q.『終活サポート』を利用した方がよい人はどのような人ですか?
A.「私が死んでも妻が困らないようにしたい」「特定の子供に多めに財産を相続させたい」「お世話になった相手にお礼がしたい」「高齢期の介護や財産管理などの問題についてきちんと事前に手を打っておきたい」「年老いて身の周りのことが自分でできなくなったときのために、子供がどのようにすればよいのかの取り決めを正式な契約書として公正証書で作成し残しておくこと」「親子なのに契約書だなんて他人行儀だ」と思われるかもしれませんが、なあなあになりやすい親子だからこそきちんとした書類が必要です。金融機関や医療機関の鉄続きができなくて困る。子供が親のために一生懸命やっているのに、他の兄弟姉妹や親族から「勝手に親の財産をおろしている。使い込んでる」と疑われたり、「不必要に親のためといってお金をかけている」などと後から文句を言われたりしてトラブルが発生することが多いです。口約束ではなく正式な書類にしておくことで、将来生じるトラブルを未然に防ぐことができます。
Q.事例を紹介していただけませんか?
A.事例1「遠方に住んでいて子供が金融機関や医療機関や役所の事務手続きのたびに、毎回親の委任状や戸籍謄本などを取得して手続きをしなければならないのは非常に煩雑です。もっと簡単な形で、親の代わりに様々な手続きを子供ができないのでしょうか?」→お子様と親御さんとの間で、金融機関の手続きなどについて委任する内容の『財産管理等の委任契約』を公正証書で作成することで、毎回の委任状が不要になります。金融機関の窓口としても公正証書で作成された契約書であればその内容の信頼性は非常に高いと判断され、その都度親御様に意思確認をすることなく、お子様1人で様々な手続きが行えます。
Q.事例を紹介していただけませんか?
A.事例2「結婚せずに独身のまま年齢を重ねた方が、将来寝たきりや認知症になったときに、誰が入院手続きやお金の管理をしてくれるのでしょうか?」→これらの手続きは本人でなければ、原則手続きはできませんし、認知症になってしまった場合はこれらの手続きをするために、法定後見の申立てをして成年後見人を家庭裁判所に選任してもらわないと、手続きができません。しかも選任されるまでは、数ヶ月から半年近くもかかり、その間手続きなどがストップしてしまうおそれがあります。このような事態になってからでは、周りの人に多大な迷惑をかけ結果としてご自身も身体的・精神的に疲弊してしまいます。元気なうちに将来の万が一に備えておきましょう。
Q.事例を紹介していただけませんか?
A.事例3「かつて父親が脳出血で入院したとき、脳の機能は停止しているのに、いくつものチューブをつながれ様々な延命措置により人工的に生かされている様子を見て、またずっと付き添っている家族の心労や経済的な負担はかなりのものでしたので、自分が同じような状態になったときには、家族を同じような目に遭わせたくないので、延命措置をしないでほしい」と思うようになりました。しかし、数年後に事故で脳死状態になっても書類が残っていなかったので、延命措置の拒絶はできませんでした。もし、無駄な延命措置を辞めてほしいという希望なあるなら、その意思を客観的に表明できる「尊厳死宣言書」を公正証書で作成することをお勧めします。
Q.『遺言書』を作るメリットはなんですか?
A.①遺産争いを未然に防げます。遺言書がないと亡くなった人が遺産をどのように分けるべきと考えていたのかわかりませんので、相続人が各自好き勝手に自分の考えを主張して話し合いがすすみません。また、相続は多くの人にとっていわゆる『たなぼた』で財産を手に入れるチャンスなので自分の取り分を多く主張しがちです。その結果、面倒を献身的に看ていた人の相続分を多くしようなどということなく法定相続分をきっちり要求するためトラブルが発生するのです。遺言書があれば、相続人は遺言者の意思に従い手続きを進めることとなり、遺産争いを未然に防げることになります。②特定の人に遺産を確実に残せます。遺言書がなければ、相続人は原則としていわゆる法定相続分の割合で遺産を相続します。しかし、残された相続人の家族の力関係によっては、不条理な遺産分割協議の結果、故人の家に住んでいた人が売却などで家を追い出されたり、もらえるばすの遺産をもらえず生活に困るといった事態が生じるおそれがあります。遺言書があれば特定の人に確実に遺産を残すことがで、その人の生活を守ることができるでしょう。③相続手続きの負担を減らせます。遺言書がないと、遺産の把握に時間がかかったり、相続手続きをするためのたくさんの書類を集めなければなりません。遺言書があれば、遺言書の記載内容から遺産の把握がスムースにできますし、相続手続きも書類が省略できる場合が多いです(公正証書遺言の場合)。
また、『老後の安心に備えて』遺言書以外の対策も必要になってきました。遺言書の必要性については広く知れ渡るようになってきましたが、遺言書が効力を発揮するのはあくまで、死亡後の話です。今は死亡する前の備えの必要性が高まってきています。①足腰や目が不自由になったり、寝たきりになった場合、②認知症などで判断能力が低下し、家族の顔も分からなくなった場合、③事故や病気により脳死状態になった場合、あなたはこのような事態に備えてどのような対策をしていますか?このような状態になったら、誰が世話をしてくれるのか?万全な介護が受けられるのか?ボケていることをいいことに悪徳業者にだまされることはないか?といった不安はありませんか?将来のこのような不安に対しての備えをしっかりすることが大切です。
Q.成年後見制度について教えて下さい?
A.成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方々を保護し支援する制度です。判断能力が不十分な方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。
Q.「任意後見」と「法定後見」の違いは何ですか?
A.「任意後見」とは、ご自身の判断能力が無くなる前に、自分の後見人になって欲しい人を『自分で』選んでおくことができる制度です。これに対し、「法定後見」とは、すでにご自身の判断能力が無くなった場合で、法律的な判断が必要になった場合に、その法律的な判断をできる後見人を選任するために、身内の方など、周囲の方が代理で家庭裁判所に申立てを行い、 『家庭裁判所』に後見人を選任してもらう制度です。法定後見人として選任される者は、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家の方々がなるケースが一般的です。
Q.「任意後見」は誰に頼めば良いのですか?
A.ご自身が判断能力がなくなった場合に、施設などとの契約や、売買契約、預貯金の出し入れなどの法律行為をあなたの代わりに行い、あなたの財産を管理する人になりますので、信頼をおける人に頼みましょう。自分の子供などの他、第三者として法律の専門家に頼まれる方も多いです。
Q.「任意後見」の契約はどうすれば良いのですか?
A.あなたが判断能力がなくなったときに施設、役所、金融機関でスムーズに手続きができるように公正証書で作成します。
Q.「任意後見」の契約に家族の同意は必要ですか?
A.家族の同意は要件とはなっていません。しかし、あなたの判断能力がなくなってしまったときに、あなたの生活やあなたの将来の生活の方針などを決める際に協力が必要になる場合がありますので、伝えておいた方がよいと思います。
Q.「任意後見」の契約に足腰が不自由になった場合でもお願いできますか?
A.「任意後見」の契約内容は、判断能力が不十分な方を対象としています。足腰など体が不自由になった場合に備えての契約は、別に、「財産管理等委任契約」があります。
Q.「任意後見」契約の「代理権目録」はどのように決めれば良いですか?
A.財産管理に関する法律事項と日常生活や療養監護等の身上監護に関する法律行為があります。ご自身で事由に選ぶことができます。
Q.「任意後見」の契約はいつから効力が始まるのですか?
A.委任者の判断能力が不十分になり、家庭裁判所に申立をし、家庭裁判所が審判にて任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。判断能力がなくなっても直ちに効力が生じるわけ出ないのがポイントです。
Q.「任意後見監督人」とは何ですか。
A.「任意後見監督人」とは、任意後見人が任意後見契約の内容どおり適正に仕事をしているかを監督する人です。また、本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに、任意後見監督人が本人を代理します。任意後見監督人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
Q.「任意後見監督人」にはどういう人がなるのですか?
A.「任意後見監督人」には、家庭裁判所により、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが多くなっています。任意後見受任者本人や、その近い親族(任意後見受任者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)は任意後見監督人にはなれません。また,本人に対して訴訟をし、又はした者、破産者で復権していない者等もなれません。
Q.「後見登記」とは何ですか?
A.「後見登記」とは、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書を発行することによって登記情報を開示する制度です。
Q.「後見」について、戸籍に記載されてしまいますか?
A.戸籍には記載されません。
Q.「後見登記事項証明書」とは何ですか?
A.任意後見契約の委任者や被後見人等が誰であるか、任意後見契約の受任者や後見人等が誰であるか、権限や代理権の範囲がどのようなのもかについて記載されている証明書です。
Q.「後見登記事項証明書」はどういうときに使いますか?
A.任意後見契約の受任者や成年後見人が、委任者や本人に代わって法律行為をする場合にその権限を証明するために使います。具体的には、任意後見契約の委任者や成年被後見人に代わり、財産の売買・介護サービス提供契約などを締結する時に、取引相手に対し登記事項証明書を提示することによって、その権限などを確認してもらうという利用方法があります。
Q.「後見登記事項証明書」はどのように取得します?
A.窓口で取得する場合は、東京法務の民事行政部後見登録課及び全国50ヶ所の地方法務局の窓口です。千葉県では、千葉地方法務局です。郵送の場合は、東京法務局のみです。
Q.「後見登記事項証明書」は誰でも取得できますか?
A.誰でも取得できるものではありません。本人、本人の配偶者、本人の4親等内の親族、本人の成年後見人等のみです。取引の相手方を理由に請求することはできません。
Q.「後見登記事項証明書」はどれくらい有効ですか?
A.提出先により異なりますが、一般的には、3ヶ月以内のものを提出するように要求されます。
Q.「死後事務委任契約」とは何ですか?
A.『死後事務委任契約』とは、委任者(本人)が第三者に対して、亡くなった後の様々な手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。遺言書ではカバーしきれない事項を決めておくことができます。
Q.「任意後見契約」と「遺言」の関係はどうなりますか?
A.「任意後見契約」は、判断能力がなくなったときに効力が生じるもので、「遺言」は、死亡した時に効力が生じるものです。よって、抵触するものではありません。
Q.「任意後見契約」「遺言書」「死後事務委任契約」を同時に作成できますか?
A.同時に作成できます。それぞれが時間を異にして効力を生じるものですので、同時に作成しておいた方が将来にわたり、幅広く備えることができるでしょう。
Q.「認知症」が始まっていますが今から「任意後見契約」はできますか?
A.「任意後見契約」も「契約」ですので、判断能力がなくなってしまっているのであれば、「任意後見契約」はできません。法定後見を申立てることになります。
Q.「任意後見契約」の中に『尊厳死』の希望を書けますか?
A.「任意後見契約」の中に『尊厳死』の希望を書くことはできません。別途、『尊厳死宣言公正証書』を作成することになります。
市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターによる
『終活サポート』4つの特徴
全て公正証書で作成します。
・終活に関する契約書は全て公正証書で作成します(市川・船橋の公証役場)。
・万が一の時にご家族の方の手続きがスムーズになります。
後見・相続の専門家が対応します。
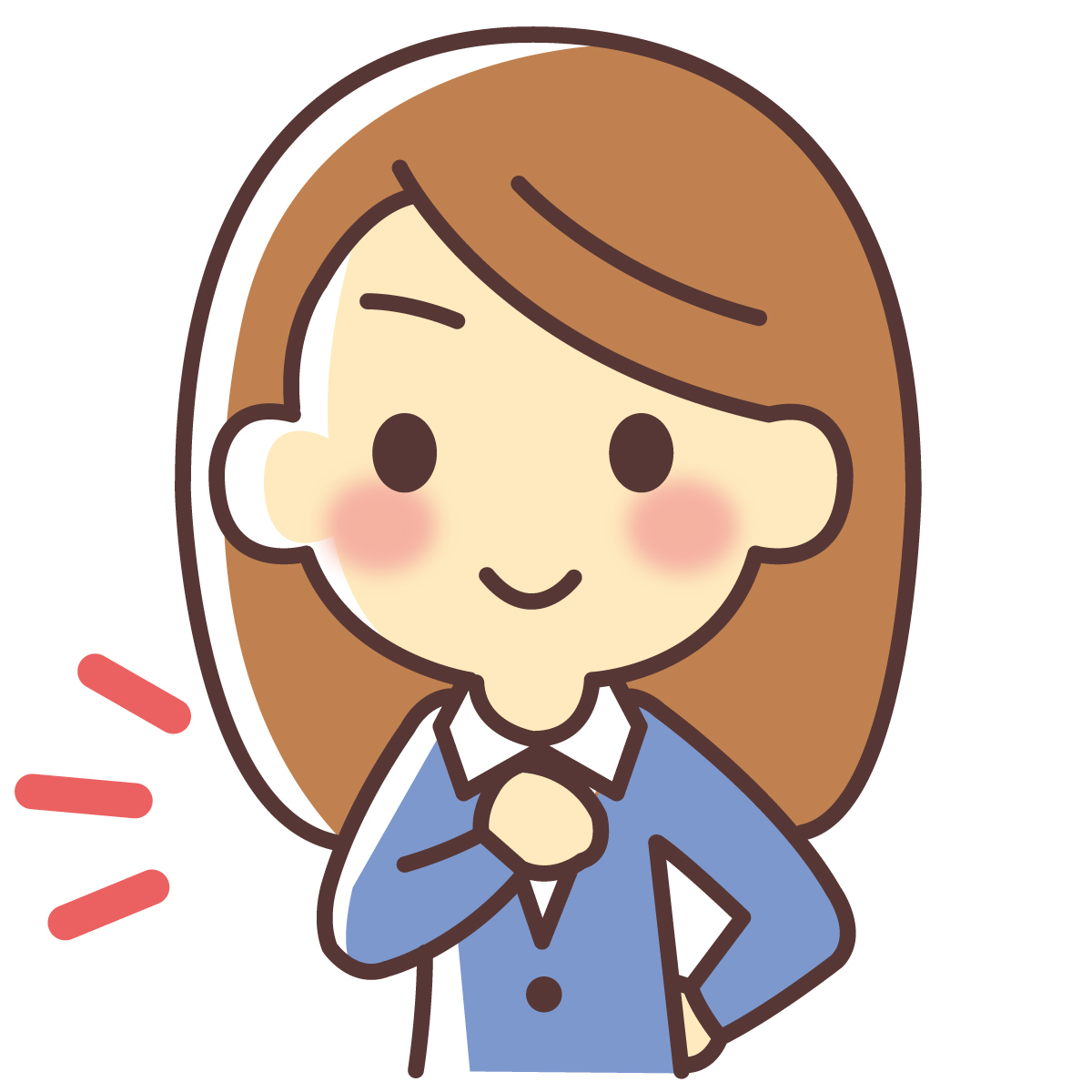
・成年後見業務・相続手続きに強い司法書士、行政書士が対応します。
・将来のために備えた契約をアドバイスいたします。
無料訪問相談を実施しています。
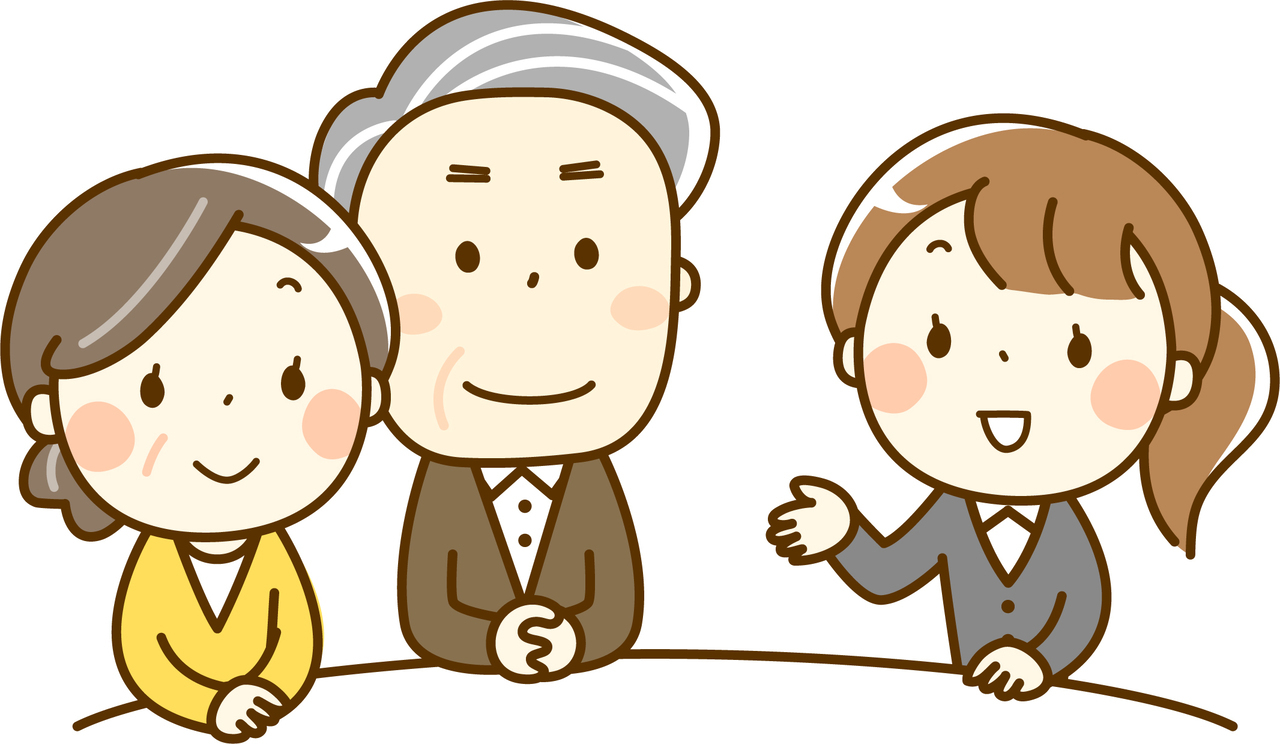
・お客さまごとにきちんとお時間をとり、無料でご自宅・病院・その他施設へ伺いじっくりお時間をかけて丁寧に説明させていただきます。安心してご相談ください。
・土日などご家族の方が集まるときに伺うことも可能です。
時間をかけてカウンセリング。
・お客様ごとにじっくりご相談させて頂くため、一日一組のご対応となっております。
・ご予約は、お電話もしくはお問い合わせフォームからお願いします。
市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
が選ばれる4つの特徴
無料で訪問相談を実施しています。
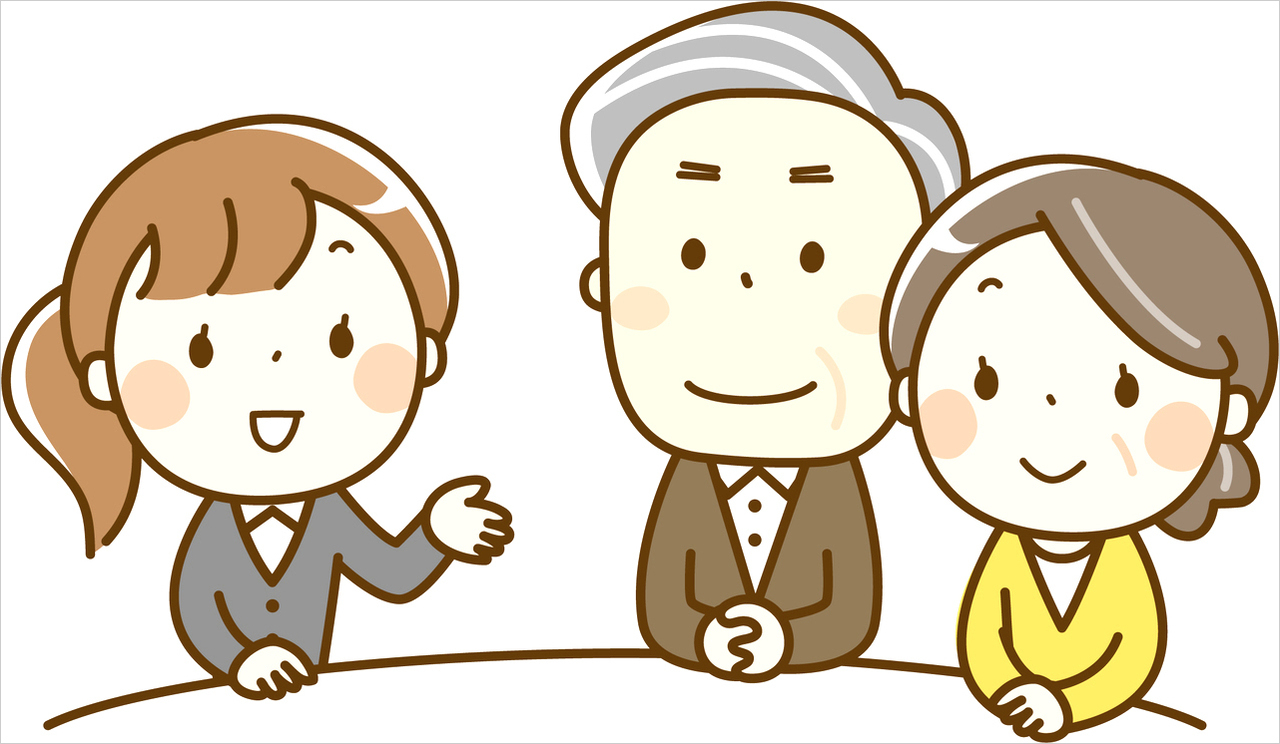
相続・遺言・終活の相談は、相談員がご自宅へ訪問し、じっくりとお話をうかがいます。
- メリット1 ご相談の際に、戸籍謄本、不動産の権利証、預金通帳などを確認させていただく必要があります。このような大切な書類を家から持ち出すと、紛失・盗難などに遭う危険性があります。私どもの相談員がご自宅で書類を確認させて頂きますので、紛失・盗難などの危険性を避けることができます。
- メリット2 事務所へ相談にご来所いただいたお客様の多くが、緊張しておられました。そのため、お客様のご自宅やご指定の場所でリラックスしてお話をして頂けるよう、私どもが訪問するという形でご相談をお受けしております。
- メリット3 ご自宅に訪問という形を取ることで、その場で必要書類を確認させて頂くことができます。ご来所頂いた場合と異なり、確認のための書類を再度持参して頂いたり、書類を郵送してもらうという手間を省くことができます。お客様の煩わしさの解消になっております。
- メリット4 ご自宅やご指定の病院・施設等への出張費は無料です(市川市、船橋市内に限ります)。
相続手続・遺言書作成・終活に強い司法書士・行政書士が対応します。
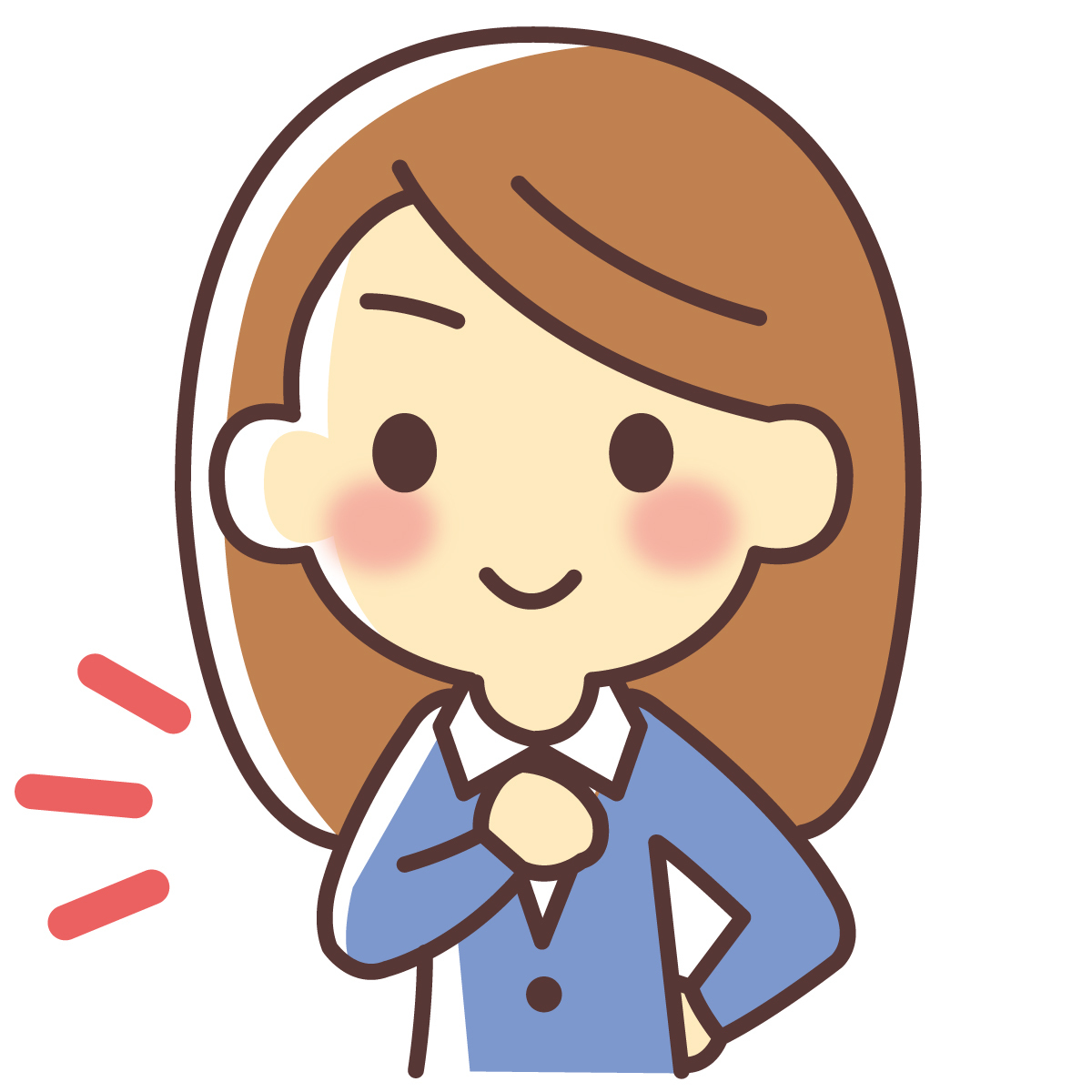
相続手続・遺言書作成・終活を得意とする司法書士・行政書士が直接対応いたします。
- メリット1 「士業」といわれる専門家といってもその全ての業務に精通することは困難です。お医者さんに、内科医・外科医など得意分野があるように、士業にも得意分野などがあります。私ども市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員は、相続手続・遺言書作成・終活を得意としています。
- メリット2 スタッフは全員、司法書士・行政書士など国家資格をもった専門家です。
- メリット3 お客様とのやりとりは全て司法書士・行政書士など国家資格を持った専門家が直接ご対応いたします。専門家は守秘義務が課せられているのでご安心下さい。国家資格を持っていない事務員(補助者等)が応対することはありません。
市川市・船橋市を中心にサポート業務を行っています。

地域密着として市川市・船橋市のお客様からご依頼をいただいております。
- メリット1 市川・西船橋・船橋・原木中山・下総中山・本八幡・妙典・行徳・南行徳といった、地元の市川市・船橋市をメインに業務を行っています。
- メリット2 戸籍収集や各種書類の取り寄せは全国の市役所対応です!
- メリット3 地元市川市・船橋市の金融機関のみならず、全国の金融機関の相続手続が対応可能です!
安心・明瞭・低価格な料金設定。
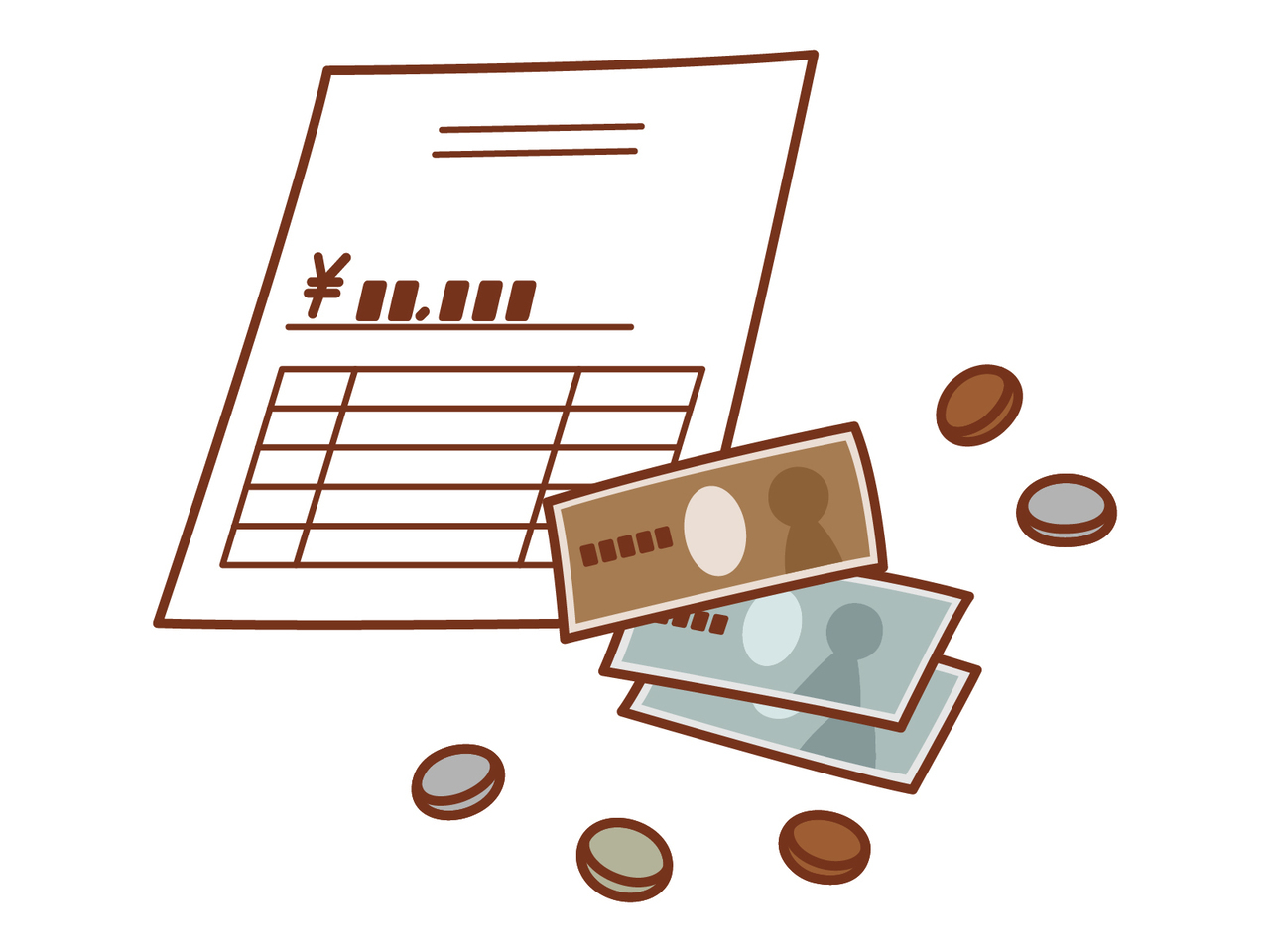
各手続きサポートに「基本プラン」を設定しております。
- メリット1 各サポートごとによくある一般的な事案に関しての報酬を「基本のプラン」として設定しております。
- メリット2 各サポートごとにおおよその目安となる報酬の例をご案内しています。
- メリット3 全国の役所からの書類取寄せ業務・金融機関の名義書換手続業務につき遠方の割り増しなど一切ありません。
- メリット4 面談の訪問の出張費費は一切頂いていません。相続・遺言・終活の相談は無料です。訪問時の出張費も無料です。
- メリット5 無料の電話相談も行ってます。お気軽にお電話ください。→無料の電話相談の日時など詳しくは、こちらをクリック。

お気軽にお問合せください。
受付時間:9:00〜18:00
事前にお電話頂ければ上記時間外も対応いたします。
(事前にお電話頂ければ土日祝も対応いたします)

市川市・船橋市にお住まいの方へ
相続・遺言・終活に関する
無料訪問相談の24時間予約可能のフォームはこちら
相談料無料・出張費無料・無料訪問相談実施中です!
市川・船橋 相続・遺言・終活
相談センターのご案内
住所
〒272-0014
千葉県市川市田尻四丁目3番2号
原木中山駅から徒歩5分
市川市・船橋市に
お住まいの方へ

相続・遺言・終活に関する無料訪問相談のご予約は下記から
お知らせ
司法書士による相続・遺言・終活に関する無料の電話相談のご案内!
内容:相続手続・相続放棄・遺言書検認・遺言書作成・終活。
目安:お一人様20分程度。
対象:市川市・船橋市の方。

市川市・船橋市の方へ
相続・遺言・終活に関する電話相談をいたします。
お気軽にお電話ください。
相続・遺言・終活に強い司法書士がご対応いたします。予約不要です!